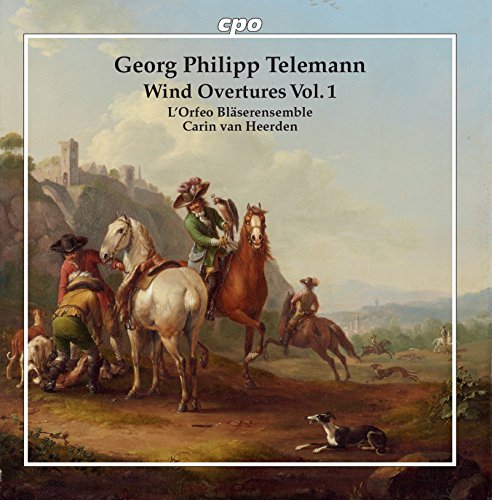吹奏楽のたどってきた道について、具体的な楽曲というものが残っていない時代にまでひとまず遡るとして、管(打)楽器はおもにその音量ゆえに、権力者がその威を振るう必要がある場面、あるいはそこまでいかなくとも共同体の結びつきと関わるかたちで役立てられてきたことが多いとは言えるでしょう。遅くとも古代エジプトではリード式・エアリードによる笛、リップリードによるラッパが揃っており、後年の用法につながるような、軍楽としての制度的な利用も現れていました。ギリシアやローマにおいても軍楽などで金管楽器の活用がみられたほか、アウロス aulos もしくはティビア tibia(おもに二股状のリード楽器)のさまざまな用例が記録されています*1。
なお管(打)楽器による合奏という形態がどこで現れたかはよくわかりません。トトメス4世時代(紀元前十四世紀ごろ)の壁画には二人のトランペット吹きが並んで描かれていますが同時に演奏していたかは不確かです。古代ギリシアで多く用いられていたアウロスは平時には一人のみで演奏するのが通例でしたが、複数のアウロスとともに行進するスパルタの軍隊の習慣にトゥキュディデスが言及しています。
西ローマ帝国衰退後、ヨーロッパにおいて器楽合奏の組織は下火になっていましたが、インドや中東において、12世紀には軍隊に随行するかたちでの管打楽器の活用が生まれました。このころの十字軍参加者の記録には、敵軍の軍楽の大音響に圧倒されたことが記されています。
おそらくはその影響を受けて、中世盛期から後期にかけてヨーロッパのあちこちで、権力者の威厳を演出するために恒常的に音楽を利用する例が増えていきます。そういった場に向いたであろう管楽器によるアンサンブルの存在は13世紀には確認されており、イスラム世界からの影響で(再)導入されていたと思われるトランペットや、ダブルリード楽器のショーム、太鼓が用いられていました。
祭りのときなどにメネストレル ménestrel やジョングルール jongleur と呼ばれるような流しの楽師/大道芸人を雇い入れるような例はかなり早くからありましたが、権力者が楽師たちと一定期間の雇用契約を結び、折にふれて音楽を演奏させる例が増えていったのがこの時期の動きです*2。
なお、当時の職業音楽家たちは基本的に複数の楽器(場合によっては歌も)を習得しており、求められた場に合わせるかたちで異なった楽器を演奏していました*3。すくなくとも14世紀には登場していた楽器の分類法に、「オー」haut("高い"/音の大きな)と「バ」bas("低い"/静かな)の区別があります。リード楽器・金管楽器や打楽器などを含む前者は屋外や、大人数が集まる開けた場に向き、笛や擦弦楽器・撥弦楽器などが含まれる後者は室内の、小規模な場に向いていて、多くの場合この二種は分けて用いる規範がありました。現在から振り返って「吹奏楽」の歴史を構成するのは、この「オー」に属する合奏ということになるでしょう。
ショーム属と金管楽器によるアンサンブルは、のちに中音域のショームを加え、15世紀には出せる音の多いいわゆるスライド・トランペット*4が導入されて自由度が増し、対応できる音楽の幅が広がります。アルタ alta(これも "高い"/音の大きな、の意)やアルタ・カペラ alta cappella などと呼ばれた、通常三、四人からなるこのようなアンサンブル――具体的な楽器選択には揺れがありえます――は、式典や祭り、宴会、踊りの場、また宗教的な性格の行列や儀礼の場などさまざまな場面で必要とされ、権力者にとどまらずときには市民に依頼されるかたちで、音楽を提供していました。
時代が下るにつれ、規模の大小こそあれ宮廷がこうした楽団を持つのは標準的なこととなり*5、いっぽうで各地の宮廷だけでなく、ヨーロッパじゅうの都市が音楽家を――おそらく高所からの見張りの役職が発展するかたちで――雇っていました。とくにシュタットファイファー Stadtpfeifer と呼ばれる、ドイツ語圏諸都市で参事会に雇われていた音楽家たちは、J.S.バッハやテレマン、クヴァンツなどの有名作曲家とのつながりも手伝って広く知られています。
彼らの遺産であるジャンルに、トゥルムムジーク Turmmusik("塔の音楽")と呼ばれる、城壁や市庁舎などの高所から演奏された音楽があります。ライプツィヒのシュタットファイファーだったヨハン・クリストフ・ペツェルの Hora decima musicorum Lipsiensium (1670) *6や、その後輩でJ.S.バッハ作品のトランペットパートの演奏で有名なゴットフリート・ライヒェ*7の Vier und zwantzig Neue Quatricinia (1696) はコルネット(指孔で操作するリップリード楽器。ツィンクとも)とトロンボーン*8のための合奏曲集で、ペツェル作品の「ライプツィヒの十時の音楽」とでも訳せる題名のとおり、生活に溶け込んだ彼らの演奏をうかがわせてくれます。
中世からルネサンス期にかけて管楽合奏は多彩な活躍を見せましたが、このころ演奏された具体的な楽曲にたどりつくことには一定の困難が伴います。一つはそうした楽師の演奏が即興と口伝に拠るところが大きかったのと、もう一つは、管楽に限らず編成固有のレパートリーという意識がきわめて希薄で、器楽演奏においてもむしろ声楽作品として作られたものが大きな比重を占めていたことによります*9。
とはいえこうした状況を前提にありえた音を聴かせてくれる録音は少なくなく、Into the Winds "Le Parfaict Dancer: Dance Music 1300-1500" (Ricercar, 2022) は13世紀ごろのエスタンピー La Tierche Estampie Roial y Danse *10から16世紀までのさまざまな舞曲を管楽主体で録音しており、「アルタ」関連ではピッファロ Piffaro, the Renaissance Band がフランスに由来する声楽曲や舞曲を取りあげた "Chansons et Danceries" (Archiv, 1996) など多数の録音を残しているほか、Les Haulz et Les Bas や Ensemble Alta Musica 、Capella de la Torre 、Alta Bellezza といった団体*11が活発に録音を行っています。
声楽曲以外のレパートリーの供給源について見ていくことにしましょう。さきに述べたように舞曲は管楽合奏にとって重要な活躍の場でしたが、16世紀、パヴァーヌやガイヤルドなどの新しい舞曲が流行を始めるとともに、合奏舞曲の記録に変化が起こります。中音域の「主旋律」に即興的・対位法的に線が加わるそれまで多かったスタイルに代わって、上声に旋律を置き、ホモフォニックかつ明確なリズムで動くスタイルの舞曲*12が重視されるようになっていき、印刷楽譜の発展にともなって(楽譜の活版印刷は1501年に登場)広く共有され、記録がより残るようになります。
アテニャン Pierre Attaingnant やジェルヴェーズ Claude Gervaise らの出版による『ダンスリーズ』Danceries (1530-1557) 、スザート Tielman Susato『ダンスリー』La Danserye (1551) 、プレトリウス『テルプシコーレ』Terpsichore (1612) 、シャイト『音楽の遊戯』Ludi Musici (1621) といった大部の曲集や、アルボー『オルケゾグラフィ』Orchesographie (1589) といった舞踏指南書は同時代の舞曲を多く記録しています。基本的に楽器編成は指定されていませんが、もちろん管楽合奏は有力な選択肢の一つであり*13、現代においてもとくに小編成の管楽アンサンブルのレパートリーとしてよく取り上げられます*14。
のちにオーケストラの中心となるヴァイオリン(属)が普及したのもこのころで、同じ弓奏弦楽器のヴィオルなどに比べ輝かしい音色と表現の幅広さが好まれ、宮廷における舞曲などの演奏において急速に広まっていきました。
16世紀はヨーロッパ各地で多彩な器楽曲が勃興していった時期ですが、イギリスでは16世紀後半から17世紀にかけて、多声合奏(「コンソート」consort と呼ばれる)のための楽曲が隆盛を迎え、ダウランド、バード、ギボンズ、パーセルなど当時のイギリスを代表する作曲家たちも筆を執り、よく知られたジャンルになっています。当時の常で厳密な楽器指定はあまり行われませんが、ホルボーン Anthony Holborne の曲集 Pavans, Galliards, Almains and other short Aeirs, both Grave and Light (1599) に「ヴァイオル、ヴァイオリンもしくは管楽器のための」for Viols, Violins or other Musicall Winde Instruments と記されているように、リコーダーやクルムホルン、コルネットなどの管楽器で演奏されることもありました。ただし実際にコンソート音楽で重用され、上流階級のアマチュアのたしなみという一般的なイメージにあてはまるのはヴァイオルであり、管楽器はおもに、ヘンリー8世以降数代にわたって王家に仕えたバッサーノ Bassano 一族*15のような職業演奏家のものと考えられていました*16。フランダース・リコーダー四重奏団の "Browning My Dere" (Vox Temporis/Brilliant Classics, 1993) や "Bassano" (Opus 111, 2000) はリコーダー・コンソートでこの時期の合奏作品を中心に収録しています。
宮廷の管轄下における管(打)楽器の活用としては、当然ながら軍楽も重要です。トランペットは戦場において信号による統率や伝令としての役目を果たした記録が多数あり*17、しばしばティンパニ/ケトルドラムが加わってアンサンブルを形成しました。ほかにも、歩兵の統率には笛(ファイフ)や円筒型の太鼓、式典などには「アルタ」型のアンサンブルというように編成は一定しないながらも、宮廷において君主の威厳を示す業務と混交しながら管(打)楽器は役立てられていました*18。
軍楽においてどのような演奏が行われていたか、直接的な記録が増えてくるのは17世紀以降ですが、先行して軍楽を参照した音楽作品は一定数残っています*19。ジャヌカンの声楽曲 『戦い』La Guerre / La Bataille de Marignan (pub. 1528/1555) にはラッパの響きの模倣が含まれ、アイルランドとの戦いを描いた版画に触発されたと思われるバードのヴァージナル曲『戦い』The Battel (bef. 1591) では両陣営の「行進」marche やさまざまな管楽器の響き、戦闘後の踊りなどが描写されています。
カトリック教会はもともと礼拝における楽器の使用に否定的でした。しかし遅くとも14-15世紀には各地の教会にオルガンが普及し、それに次いで、教会外での宗教的な儀礼や高位の聖職者の私的楽団などを通じて接点のあった、ほかの楽器も教会で演奏するようになります。当初は声楽曲の譜面などを演奏していたと思われるこうした合奏は、オルガンの後を追ってリチェルカーレ、カンツォーナやソナタといったジャンルを発展させていきます。
教会と管楽合奏の関係に関してよく言及されるのが、ヴェネツィアのサン・マルコ寺院*20です。フランドル出身で1527年に楽長に就任したヴィラールトやその弟子たち、いわゆる「ヴェネツィア楽派」の活動の中心ですが、ヴェネツィア総督 doge の礼拝堂として世俗の式典とも結びついていた*21この寺院は器楽合奏を含む大規模な楽団を備えるようになり*22、そこで演奏される壮麗な音楽では管楽器も重用されていました。
サン・マルコ寺院のオルガニストを務めた*23ジョヴァンニ・ガブリエリの『ピアノとフォルテのソナタ』Sonata Pian e Forte (pub. 1597) は、楽譜に強弱を印刷した最初期の作品であるとともに、具体的な楽器の指定を記した最初期の作品として知られていますが、その編成はコルネット1+トロンボーン3と ″Violino″ 1+トロンボーン3の二群のアンサンブル*24からなり、金管楽器が中心になっています。おじで同じくオルガニストであるアンドレア・ガブリエリの『戦いのアリア』Aria della Battaglia (pub. 1590) *25も、具体的な楽器の指定こそありませんが「管楽器が奏する」per sonar d'instrumenti da fiato という記載があります。
ジョヴァンニ・ガブリエリの器楽作品で固めた Les Sacqueboutiers "Venise sur Garonne" (Flora, 2014) のような録音もいいですが、実際のサン・マルコ寺院での式典を想像したマクリーシュ/ガブリエリ・コンソート&プレイヤーズ "A Venetian Coronation 1595" (Virgin Classics, 1990) やキング/キングス・コンソート "Lo Sposalizio" (Hyperion, 1998) は彼らの音楽を背景も含めてより楽しめるでしょう。
彼らの作品は、現代においてもおもに金管合奏のレパートリーとして広く演奏されており*26、コーリ・スペッツァーティ(分割合奏)と呼ばれる複数のアンサンブルの対比が特徴的なその音楽は、バンド作品にもインスピレーションを与えています*27。
17世紀に入ると教会における器楽合奏も弦楽器の比重が大きくなっていきますが、宗教音楽に管楽合奏、とくに金管合奏が加わる例はさまざまな文脈のもと各地に現れ*28、ベートーヴェンやブルックナーらによる『エクアーレ』であったりリストやブルックナーらがいくつかの合唱作品を残した*29時代を経て、現在のドイツに残るポザウネンコーア Posaunenchor と呼ばれる金管合奏にまでつながります。
17世紀音楽史の大トピックの一つにイタリアを起点とする「オペラ」の勃興がありますが、関連して古代ギリシア演劇に語源を持つ「オーケストラ」が生まれてきたのもこの時期です。オペラの前身の一つとされる幕間劇 intermedio では弦管混成の大規模な楽団が動員されましたが、これは音色ごとのさまざまな小アンサンブルが場面の転換に応じて交替で演奏するもので、1600年前後の「オペラ」の成立後も祝典的な機会ではこの手法が受けつがれます。しかし予算に限りがある商業劇場などでは、(改良によって楽器が完成期を迎え)音量や機動力において柔軟な弦楽を中心に、和音楽器による通奏低音、特別な効果のために少数の管楽器という編成で器楽部がまかなわれるようになります。通奏低音のみで伴奏されるのが通例だった歌のセクションに先に加わっていったのも、弦楽合奏かあるいは管楽器のオブリガート・ソロでした。
一方フランスでは、少なくとも16世紀末から一パートに複数人を重ねて音量と表現の幅を増したヴァイオリン(族)合奏が用いられ、宮廷バレエでは弦楽(ヴァイオリン族、リュート族+ヴィオル)のみの大規模合奏がみられました。王の身近でヴァイオリン合奏を率いていたリュリは17世紀後半、大規模な弦楽に様々な管打楽器を加えた楽団を用いて華麗なバレエやオペラを相次いで発表し、ヨーロッパ中に追随者を生みます。この影響によるものかイタリアでも器楽合奏の統合が進んでいき、劇音楽の外では、17世紀末からは協奏曲という新しいジャンルがコレッリ、トレッリ、アルビノーニ、ヴィヴァルディといったヴァイオリニストたちの主導で発展しました。合奏音楽の基盤としての弦楽(ヴァイオリン族)の地位は決定的なものとなって*30、18世紀半ばの「古典的」オーケストラの定着に至ります。
17世紀には純粋器楽(曲)の独立と、器楽合奏の混成化が平行して進んでいったわけで、このことはレパートリーの残りかたにも影響したと考えられます*31が、管楽合奏という領域そのものが消えたり、根本的に性格を変えたりすることはありませんでした*32。
潤沢なリソースを有していたフランス王室において音楽家は、遅くとも15世紀末のシャルル8世の時代から役割に応じて3つに区分されていました――なお、この区分は厳格なものではなく、必要に応じて他部門の演奏に参加したり、作曲したりすることは普通で、たとえばリュリらの大規模なバレエやオペラは各部門の演奏家を総動員して上演されていました。
王室の礼拝での音楽を提供するシャペル chapelle はオルガンや聖歌隊、王の日々の楽しみのための音楽を提供するシャンブル chambre は(撥弦)鍵盤楽器や弦楽器、歌手などが属します。対して、エキュリ écurie(厩舎)は屋外をはじめとする大規模な式典や狩り、王が各地を訪問するときや客人を歓迎するときなどに音楽を担当しており*33、いくつかに区分され、多彩な楽器が割り当てられたこの組織には弦楽器を担当する(担当できる)奏者もいる一方で管楽器奏者が多数所属していました。
エキュリの音楽隊は、すくなくとも16世紀前半のフランソワ1世の時代にはショーム族を中心としたダブルリード合奏を含んでいました。くわしい変遷は不明な点が多いですがルイ13世の時代には「12人の大オーボエ隊」Douze grands hautbois と呼ばれるダブルリード族に金管楽器が加わる合奏*34が組織されるようになって、ルイ14世期にはおそらく四声構成を基本とした、ダブルリードのみの合奏が記録されています。
ルイ14世の治世は、ショームから現在の「オーボエ」*35の原型への転換が起きた時期でもあり、フランス王室に管楽器奏者や楽器製作者として仕えていたフィリドール一族やオトテール Hotteterre 一族が17世紀の後半、おそらく宮廷の需要に応じて開発をおこなったものとされます。新しい「オーボエ」は、音の大きさで知られた(トランペットに次ぐとされた)ショームより柔らかく自在な表現と音程の正確さを獲得し、弦楽をはじめとする他種類の楽器群との合奏や、小規模な室内での演奏にも向くようになりました。リュリ流のオーケストラと同様、外交上の交流や音楽家の人的交流を通じてヨーロッパ各地に普及し、1700年ごろにはかなりの地域で旧来のショームに置き換わることになります。なお同時期のフランスでは、ドゥルシアン dulcian/curtal などと呼ばれていたバスーンの原型*36から「バロック・バスーン」の開発もおこなわれていたと考えられています。
この時代には各国でさまざまな催しのための作品が多数つくられていましたが、簡便な作品はその口伝的な性格ゆえに、大規模な作品は汎用性のなさゆえに、作品が後世に伝わっていない場合も少なくありません。フランス王室の場合は、エキュリの音楽家であり、王室の音楽書庫の司書も務めていたフィリドール André Danican Philidor "l'ainé" (1647–1730) が多数の記録を残しており、フィリドール自身やリュリたちがオーボエ隊やトランペット隊などのために書いた作品に豊富にアクセスすることができます。録音としては、フランス宮廷のダブルリード合奏とその周辺を概覧する Syntagma Amici, Giourdina "Fastes de la Grande Écurie" (Ricercar, 2022) があるほか、"Musique de la Grande Écurie and des Gardes Suisses" (Musiques Suisses, 2009) や Hugo Reyne / La Simphonie du Marais "Marches, Fêtes Et Chasses Royales" (Fnac Music, 1995/Virgin Veritas, 2011) は「エキュリ」の多彩な合奏をさまざまな用途に分けて(前者は弦楽器も加えて)再現する試みです。
軍隊組織内の人員が演奏するという意味での「軍楽隊」は、スイスの傭兵部隊の横笛(ファイフ)のような例はありましたが、期待されていたのは戦場などでの統率の役割で、長らくシンプルな構成を基本にしていました*37。しかし17世紀、戦乱が続き、また常備軍の重要性が浸透すると、各地の軍隊で他声的な音楽に対応した楽団が現れるようになります。早い例でいえば、三十年戦争末期、1646年のブランデンブルクでは「大選帝侯」フリードリヒ・ヴィルヘルムのもとで竜騎兵部隊 Dragonerkompanie にショーム3本(高音2、中音域1)とドゥルシアン、打楽器による楽団が配備され、フランスでは1663年に銃士隊 mousquetaires が、やはり4声のダブルリード合奏を持っていた記録があります。こうした楽団は、いくつかの楽器を習得した専門の音楽家からなることも多く、儀礼や式典の場でしばしば演奏したほか、兵士の慰労、兵士の募集、指揮官の個人的な楽しみなどさまざまな場面*38で用いられるようになります。かつて宮廷の音楽と軍楽の境目があいまいだったのと同様に、場合によっては軍楽隊が宮廷での演奏の任務を果たすこともあったようです。
軍楽において、歩兵の規律と平時の訓練の重要性が高まるにつれて勃興したジャンルが行進曲です。隊列行進とそれを統制する音楽についての起源ははっきりしませんが、遅くとも16世紀には太鼓の規則的なリズムパターンの利用や、そこに即興的に旋律を乗せていく演奏形態の報告があります。この種の音楽が本格的に発展していくのは17世紀以降のことで、リュリが書いた『王の連隊の行進曲』Marche du Regiments du Roy (1670)*39『銃士隊の行進曲』(Première) Marche des Mousquetaires (1658) や同時期にフィリドールたちが書いた作品*40は、記譜された行進曲のかなり早い例です。
各地に広まったオーボエとバスーンを中心とする合奏*41は、宮廷や軍隊、都市の楽隊とさまざまな場所で組織され、屋外の式典から支配階級の私的な楽しみまで多様な場面で演奏する、一般的な編成の一つとなります。出発点はショーム合奏の流れを汲むダブルリードのみによる合奏ですが、18世紀に入ると、狩りの楽器として発展し大規模合奏に加わりはじめてまもないホルンが、豊かに調和した響きを求める流れのなかで中音域のオーボエ(タイユ taille)と置き替わるという変化も起こりはじめます。
もちろんこの編成のための作品も多く書かれ、掘り起こしが続けられており*42、残された作品にみられる編成は、五、六声*43によるもの(テレマンの序曲/組曲/協奏曲群*44、ヘンデルの「アリア」HWV410, 411 とメヌエット HWV422, 423 など)から、オーボエ2+バスーン1(+通奏低音)というミニマルなもの(ゼレンカの6曲のトリオソナタ ZWV181 、J.F.ファッシュの作品群*45、ヘンデルの行進曲 HWV418など)まで幅があります。
ほかにも、さらに独奏や独唱が入って絡むもの(モルターのトランペットのための協奏曲群*46、テレマンの四重奏曲/協奏曲 TWV43:D7*47、ヴィヴァルディのヴィオラ・ダモーレが加わる『室内協奏曲』RV97、J.S.バッハのいくつかのアリア*48など)、協奏曲における小アンサンブル/独奏群として機能するもの(テレマンの協奏曲 TWV53:C1, d1, g1, 54:D2 など、ファッシュの協奏曲 FWV L:B4, c2, D16-20, D22, Es1, F2, F5, G10 など、ヘンデルの「2つの楽団のための」協奏曲群 HWV332-334 など*49)、さらにトランペット合奏*50などとともに大規模なオーケストラの一セクションを構成するもの(テレマンやJ.S.バッハなどの管弦楽組曲群、『ブランデンブルク協奏曲』第1番など)が存在し、活躍ぶりの多彩さを見ることができます。
ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル Georg Friedrich (George Frideric) Handel (1685-1759) の『王宮の花火の音楽』Royal Fireworks Music (1749) は、当時 "grand overture of warlike instruments" と呼ばれることがあったように、管打楽器のみの大合奏の依頼に応えて*51書かれた作品です。
自筆譜に書きこまれた、六十人ほどを要する編成は異例の大がかりさ*52とはいえ、オーボエ3または2+ホルン3+バスーン2(+コントラバスーン)のオーボエバンド*53にトランペットとティンパニを加えたものと整理することができ、既存の伝統の延長線上で理解が可能です。イギリスでは、早くも1670年代にはフランス趣味のチャールズ2世のもとでフランス式の新しい「オーボエ」が導入されており、18世紀初頭に王位に就いたアン女王は即位前からオーボエバンドを好んでいたことが知られ*54、なにより前述のようにヘンデル自身がすでにオーボエバンドのための作品をいくつか書いています。またオーボエバンドにおいて一パートを複数人で重ねること自体は珍しいことではなく、Johann Philipp Krieger の Lustige Feld-Music (1704) では屋外の演奏で人数を増やすことが推奨されていますし、もともとのリュリのアンサンブルも四声を十人前後で演奏した記録があります。
独立した発想ではないとはいえ、繰り返しになりますがこの規模の管楽合奏が組織され、しかも楽曲と結びつけて記録が残ることはそうありません。現代のシンフォニックバンドに類比できるような*55この作品の大編成は戦争終結の祝賀という前提と、大陸での戦争に親征するほどのジョージ2世の軍事好きとが影響した特別な機会ゆえのものですが、それが楽譜上に記録され、そして作曲者と楽曲が(管弦楽曲として)知名度を確立していたことで、この作品は「吹奏楽」の祖先の一つという地位を与えられることになったのでしょう。
さすがの有名曲で、管楽編成の録音に絞ってもそれなりの数の選択肢があります*56が、ここでは明るく整ったサウンドによるピノック/ザ・イングリッシュ・コンサート盤 (Archiv, 1999) を推薦します。ほかには若干控えめな編成による Matthias Maute / Montréal Baroque 盤 (ATMA, 2005) も、祝祭的な空気は保ったまま作品の異なる側面を見せてくれます。